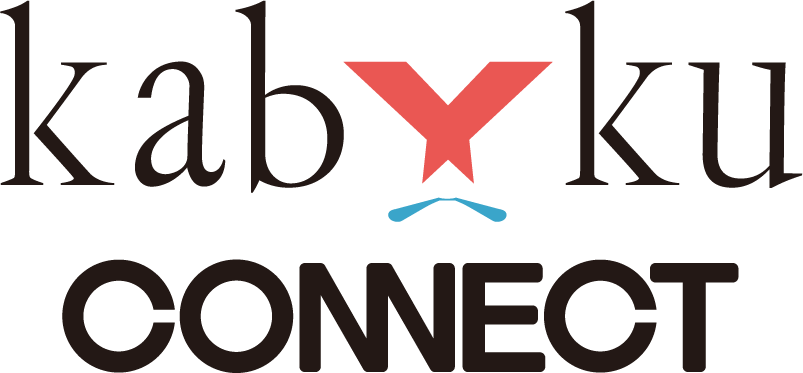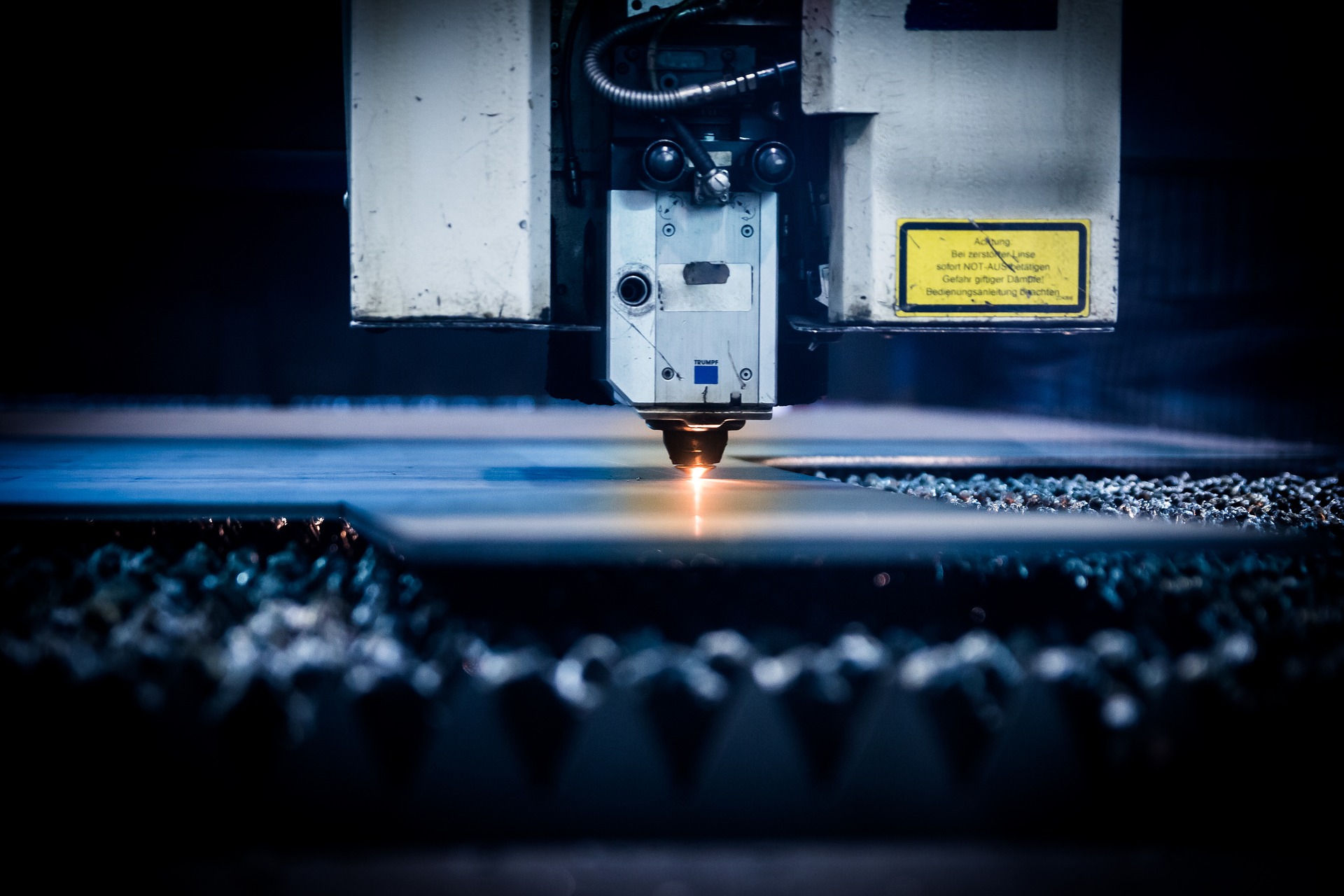【溶接】スポット溶接
スポット溶接(Spot welding)とは
2枚以上の金属板を電極で挟み、電流を流して加熱しながら加圧することで、接合部を局所的に接合する方法です。
溶接作業はスポット溶接機によって行い、概ね1秒程度で完了します。
メリット
加工が高速なので、量産に向いています。
母材のゆがみや変形があまりありません。
通電と加圧によって接合するので、溶接棒やガスなど消耗品が不要です。
溶接作業は溶接機が行うため作業者によるバラつきが出にくく、初心者でも扱えます。
デメリット
加工可能な厚みや材料に制限があります。
他の溶接と比較して、気密性が得られないこと、強度が高くないといった点があります。
スポットの間隔は、少ないと強度が弱く、多いと熱による影響が出るなど、設計者に知見が必要です。
接合部が外から見えないので、加工不良が見つけ難いことがあります。
材料と板厚
加工可能な板厚や精度は、使用する材料とスポット溶接機の能力によって異なります。
電気抵抗により金属板を加熱・融解させる仕組みなので、材料によって向き・不向きが異なります。
また、重ねた金属を挟みこんで接合することから、溶接可能な板厚に限界があります。
良く使われる材料
・SPCC等の軟鋼
スポット溶接に最も適した材料です。
板厚(目安):約8mm
・ステンレス系
熱伝導が低いため、スパッタが発生しやすいことに注意が必要です。
板厚(目安):約6mm
・アルミ系
熱伝導と導電性が高いので、大電流が必要になることから、溶接機によっては加工不可になります。
板厚(目安):約4mm
・銅や真鍮
電気伝導率が非常に高いこと、表面に酸化銅が発生しやすいことから、難易度が非常に高くスポット溶接には不向きです。
発生しやすいトラブルと対策
ナゲット不良
ナゲットとは、金属が溶融して凝固した接合部のことです。ナゲットが小さかったり、位置がズレたり、不安定(不均一)になることです。想定した強度が得られず、母材が剥がれる恐れもあります。
対策1:パラメータの改善
電流や加圧、通電時間などが不足している場合は、溶接パラメータを見直すことで改善できます。
対策2:板厚(溶接機の性能)の確認
溶接機の性能以上に厚すぎる板材をスポットしていないかをよく確認しましょう。
対策3:板厚の異なる材料を使用する場合事前に調整する
ナゲットが中央付近にできることから、板厚の異なる材料をスポットする場合、ナゲットの位置が母材の接合面よりも、厚い方の板側にできてしまい、強度が低下してしまいます。電極を非対称にするなど、接合したいところにナゲットができるように調整しましょう。
材料の組み合わせ
異種金属の組み合わせでは、熱伝導率や電気抵抗が異なるので、適切な溶接条件を設定する必要があります。
対策1:電極のメンテナンス
繰り返し使用していると、電極が摩耗や変形してしまいます。また、電極に埃や汚れが付着しているなど、接触不良を起こしている場合もあります。電極は定期的なメンテナンスが必要です。
対策2:母材表面の前処理
埃や油などの不純物や、表面被膜が厚いなど、通電の妨げにならないように、脱脂や研磨のような前処理を忘れずに実施しましょう。
スパッタ過多
スパッタという、溶融金属が飛び散り冷え固まって付着した粒が多く発生することがあります。スパッタが多いと、表面に凸凹して見えるなど外観不良や、場所や大きさによっては部品同士が干渉して使用できなくなることもあります。
対策1:パラメータの改善
通電時間が長すぎる、電流が過大、加圧力が不足している場合は、溶接パラメータを見直すことで改善できます。
対策2:材料と表面処理の選定
亜鉛メッキ(亜鉛メッキ鋼板)は、スポットが難しくなり、スパッタが発生しやすくなります。さらに、亜鉛が溶融することで、電極に付着する、酸化亜鉛が発生するなど、いくつかの問題が発生します。問題がなければ、他のスポットしやすい材料に変更するか、スポット後にメッキをするなどの対策が必要です。
対策3:スパッタ防止剤の使用
飛散したスパッタの付着を防ぐために、スパッタ防止剤を使用します。母材にスパッタが付着しにくくなることで、除去する作業工程がなくなり、作業効率が向上します。電極など溶接機の部品への付着も防止できるので、交換する頻度を少なくできます。