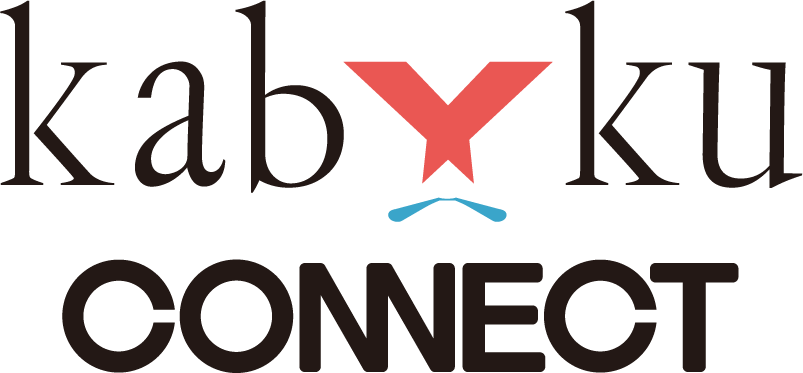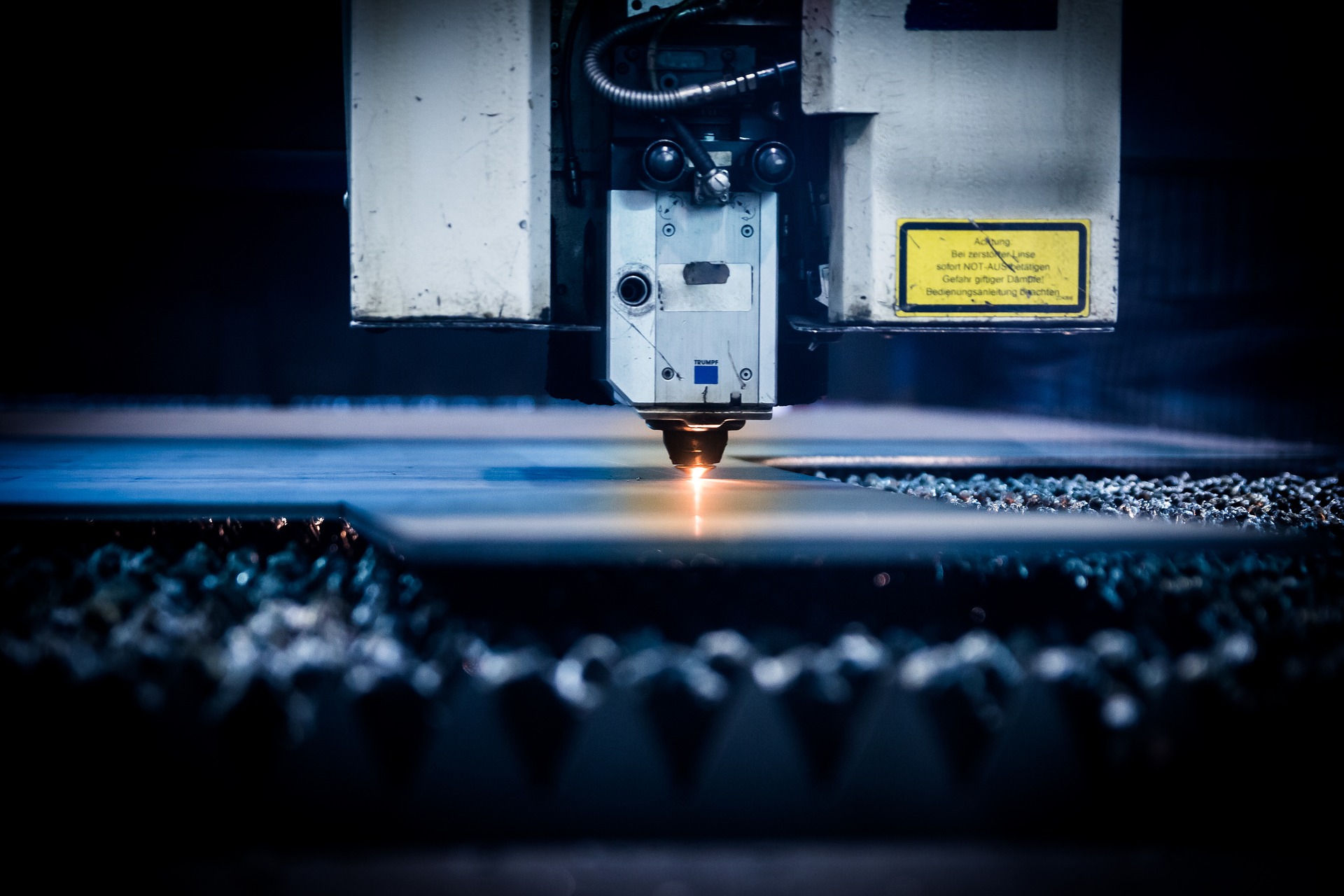【部品】機械設計の基礎:機械要素 配線の基礎知識
配線とは
電気で動作する機械・装置の内部や外部で、電気を供給・制御・伝達するために電線やケーブルを接続する重要な作業です。全ての配線が正しく接続できていないと、装置が動かない状態や、火災が発生することもあります。
1.配線によく使われる部品
①電気を通すための部品
・電線
電気を通すための線のことで、心線に触れても感電しないように絶縁体で被覆した部品です。
導体には主に銅が使われています。絶縁体は塩化ビニルやポリエチレンなどが使われています。
また、数多くの色を選ぶことができ、色を変えることで行先や分類を分かりやすくできます。
・ケーブル
複数の電線をまとめて、シースで被覆した部品です。シースで被覆することで、鋭い物や尖ったものと接触した時に電線の損傷を防いだり、屋外で使用する場合は環境からの影響による劣化を防ぐことができます。
・ハーネス
電線やケーブルの端末に接続するための部品を取り付けて、接続しやすくした部品です。圧着端子やコネクタなど、様々なものがあります。
※心線とは
電気を伝えるための導体で、線状に加工された金属のことです。「心線」と「芯線」と表記が違うことがありますが、意味は全く同じです。JIS規格では「心線」と表記されていますが、「芯線」と表記しても間違いではありません。
②端末部品
・圧着端子
一般的に使われている、心線にかしめてコネクターなどに接続する部品です。電線のサイズと端子のサイズを合わせる必要があります。圧着工具などの工具が必要です。
・差し込み端子
心線を手で差し込んで接続する部品です。適切に差し込む必要はありますが、作業自体は簡単なので効率の向上が期待できます。ただし、屋内機器にしか利用できない場合が多いので注意が必要です。
・はんだ端子
端子に心線を巻きつけた状態ではんだ付けをして固定する部品です。低コストでできる半面、衝撃や引っ張りなどの負荷に弱く、作業者の技術力によって品質に差が出やすいため、はんだ不足や熱のかけすぎなど、不良に繋がるので注意が必要です。はんだごてを使用し、保護メガネや耐熱手袋を使用する場合もあります。
2.工具
・ワイヤーストリッパー
心線を傷つけることなく電線の被覆を剥くための工具です。電線の規格とサイズに合わせて使用します。刃物やニッパーを使って被覆を剥いて心線をキズづけてしまうと、キズ部分が折れたり切断されることで、抵抗値が変化して異常発熱により発火する恐れがあります。
・圧着工具(圧着ペンチ)
圧着端子を電線に圧着するための工具です。圧着端子の種類とサイズに合わせて使用します。合わない工具やペンチなどの工具を使用すると、圧着できているように見えていても、被覆が切れて電線が露出してショートの原因になったり、締まりが緩くて電線が抜けてしまうこともあるので、適切な工具を使用します。
・はんだごて
端子と電線をはんだ付けで接合するための工具です。はんだを加熱して溶かすため、非常に高温になります。火傷や事故を防止するために取り扱いには注意が必要です。
・電気テスター(マルチメーター)
電圧、電流、抵抗値などを測定するための計測器です。ハーネスの検査に使用します。ハーネス加工後に、付け間違いや内部の断線を目視では確認できないので、計測器が必要になります。
3.便利な小物
・タイラップ
ハーネスを簡易的に束ねる為に使用します。シースとは違い、現場で纏めることができます。100円均一のお店でも購入でき、家庭でも使われています。独自の呼び方をしている人が多いので、気を付けましょう。(結束バンド、ケーブルタイ、バンドなど色々あります。)
・コンベックスベース
タイラップと組み合わせて、ハーネスを固定するために使用します。裏側の両面テープで貼り付けたり、ねじ固定できる物もあります。こちらも独自の呼び方をしている人が多いので、気を付けましょう。(マウントベース、ペタ板、十字ベースなど他にも色々)
・ラベルプリンタ
配線番号や行先などの識別ラベルを印刷します。識別ラベルを貼り付けることで、配線作業のミスを削減することに効果的です。